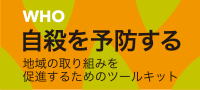東京都監察医務院訪問記 ―院長福永龍繁さんに伺う―
日本では外因死を含む異状死の死因を明らかにする監察医制度は、限られた発達しかみなかった。急激に社会が変化する今、気がつかないうちに、見えにくい、新しい死因も生まれている。死因を知ることは、安全な社会づくりにつながっている。福永さんに、監察医制度が果たしてきた役割について、お話を伺った。
まとめ:杉山春(ルポライター)
東京都にある死因究明施設
東京都文京区にある東京都監察医務院(以下監察医務院)の入り口を入ると、受付があり、その前に椅子が並んでいる。内装に木材をふんだんに使い、家族や親しい者を突然亡くし、悄然とする人たちを柔らかく受け止めようとするかのようだ。
ここは、23区内で発生した、すべての異状死―死因不明の急性死や死後発見までに時間が経ったもの、事故死(外因死)など―の検案と、必要に応じて解剖を行って、その死因を明らかにする都の施設だ。検案とは死亡を確認し、死因、死因の種類、死亡時刻等、医学的判断をおこなうことをいう。遺族らがここで死体検案書(死亡届)を受け取り、行政に提出して、一人の生涯が閉じられる。
検案・解剖を行う医師を監察医といい、その業務を行う施設が監察医務院だ。
この庁舎は2014年7月、改築後最新の機器を備えて再開した。院長の福永龍繁さんは「人が受ける最期の医療です」と語った。
渡されたパンフレットには「死亡された方の人権を擁護するとともに、死因究明の過程で得られた貴重な情報は、医学教育、臨床医学、予防医学などに還元され、医学の進歩に大きく貢献します」と記されている。
高い専門性
監察医務院は死因の解明から集まるデータを解析し、積極的に公表、社会を動かして来た。
その具体例は後に改めてお伝えするとして、2015年に扱った検案数は1万3425体にのぼる。解剖は2314体だ。東京都23区内の全死亡者数の約18パーセント、5・6人に1人がここを通過していく。これに13人の監察医、14人の臨床検査技師らと50名を超える非常勤の医師で対応する。
警察から連絡を受けて、監察医と監察医補佐、運転手の3人がチームとなって現場に出かけていく。遺体が持ち込まれる場合もある。外側から診断して死因がわかる場合はそこで診断書が書かれる。分からなければ解剖される。解剖班は監察医、臨床検査技師、監察医補佐の3人でチームを組む。
福永さんに案内されて、施設内を見せていただいた。
バイオハザード型解剖台が6台。そのうちの1台は、特殊感染用。空気の流れを作り、気圧を下げた解剖室に置かれ、感染症の遺体を扱っても外に汚れた空気が漏れ出さない仕組みになっている。
胃や血液、尿などに含まれる、気化しやすい化合物の同定定量に用いられるガスクロマトグラフィー、薬毒物を分析するための液体クロマトグラフィーや最新の質量分析装置も置かれ、有機化合物、無機化合物を検出できる。
病理組織を取り標本化して顕微鏡で病変を確認する病理組織検査の機器や、画像検査のためのCT撮影の装置がある。
監察医制度がない地域が8割を超える
日本では、医師の管理下で亡くならなかった場合、警察に届けられる。そこで警察官が犯罪性の有無を確かめる。多くの場合、警察医が立ち会う。犯罪性のある遺体は、警察署に運ばれ検視され、必要に応じて司法解剖が行われる。日本全国どの都道府県もこの司法解剖はあり、警察の要請に従って、その自治体にある医科系大学の法医学教室が担当する。
犯罪性がないとされた遺体は、監察医制度があるところでは、監察医により検案が行われ、死因がわからない場合には行政解剖が行われる。監察医制度は現在法律上、東京23区内、大阪市、神戸市、横浜市、名古屋市に置かれている。ただし、十分に機能しているのは東京23区、大阪市、神戸市のみともいわれている。
監察医制度がないところが人口の8割を超えているのだ。なお、そうしたところでは地域の医師が検案し、死亡届を書く。特に必要な場合のみ、遺族に承諾を得て基本的に公費で解剖する。その数は道府県ごとに年間数体から数十体。監察医制度がある地域に比べて解剖数は格段に少ない。なお、監察医制度は法律上は遺族に承諾を得なくても解剖は可能だ。
院長の福永さんは「犯罪性の有無を決めるのは警察ですが、死因を決めることができるのは医師です。死因の特定には、病理学と法医学に精通している必要があり、非常に専門性の高い分野です」
と語る。死の扱い方に強い地域差があるのだ。私たちは科学的に死を取り扱うことが、不得手なのかもしれない。
だが、死因の確定が求められる場面は増えている。
「交通事故死でも、警察が綿密に現場を調べ、被疑者に事情聴取をするでしょう。でも、嘘をつく場合もあるかもしれない。ご遺体の傷のつき方からは、車がどの角度で当たったかが正確にわかる。裁判に正確な証拠が提出できる。保険金のトラブルも客観的に判定できる。遺体から正確を期して作られたデータだからです」(福永さん)
発信が社会を変えてきた
それだけでなく、公衆衛生の発展のためにも、死因に関するデータはとても大きな力を発揮する。そんな事例をいくつか紹介しよう。
例えば飛行機などでの長時間の移動中、足を動かさないことにより、血流が滞り血栓ができる、エコノミー症候群の発見がある。ふくらはぎでできた血栓が血管を移動し、肺の血管を塞いで死に至る症状だ。体の外からの検案だけでは病死にしか見えない。これを発見したのは、監察医務院だった。今や、飛行機で長時間移動するときには、エコノミー症候群に備えて水分をしっかりとり、足をこまめに動かすなどの対策が常識になった。
こんにゃくで作られたゼリーで喉を詰まらせる高齢者の存在を知らしめたのも監察医務院だった。製造者は製造方法を変え、警告のイラストや文章を製品に書き込むようになった。
近年、夏になるとメディアは、クーラーをつけて水分補給をするようにと広報する。夜もクーラーをつけて寝ることが推奨される。これは監察医務院が、高齢単身者の死因を調べる中で、クーラーをつけるのをためらった末の熱中症による死亡例を多数発見したためだ。夜、涼しく過ごすことが重要だという認識は、広がりつつある。
脱法ドラックが出回り始めた頃、警察は覚醒剤や麻薬以外を取り締まることができなかった。福永さんは言う。
「当初、危険ドラックは法律違反ではなかったので、警察は司法解剖はしなかった。ここで遺体を解剖することで、物質の構成がわかりました。危険ドラックの場合、自分の寝室で静かに亡くなる場合も、公衆トイレで暴れて亡くなる場合もあることがわかってきました」(福永さん)
現在、危険ドラックは、化学構造が類似している多くの薬物を指定薬物として包括指定することで取り締まりの対象になった。
子どもの死にも関わる。
赤ちゃんには乳幼児突然死症候群(SIDS)という突然死がある。子どもが亡くなっている現場に駆けつけた警察官が母親に罪を被せないようにと事件化せず、司法解剖を躊躇することもあった。
「ところが、2003年に厚生労働省が赤ちゃんのうつぶせ寝をやめるように通達を出してからはSIDSによる死亡事例が極端に減りました。SIDSの陰に窒息死が多く隠れていたのです。もしあのまま、現場での解明を怠れば、海外の公衆衛生からみれば、日本だけがSIDSに別の判断基準を設けていることになってしまいます」
正しい死亡データは、国際社会のなかで責任ある発言をしていくためにも重要だ。
監察医務院でも、親たちはわが子の遺体の解剖をいやがる。
「それでも職員が説得します。この子を火葬してしまえば、もう何も分からなくなります。必ず将来、自分のお子さんがなぜ亡くなったのか知りたくなりますから、と。また、次に生まれてくる子どものためにも、同じ病気で苦しむ子どものためにも、事故で亡くなる子どもを防ぐためにも解剖は絶対に役に立ちますと話します」
GHQの要請で始まった歴史
死を科学的に判定する監察医制度は、1946年にGHQから東京都への申し入で始まった。当時、上野駅周辺の薄暗い地下道で死者が出ていた。人が亡くなるたびに行政と警察が来てガリガリに痩せた遺体を引き取って焼いていた。
「その死因がメチルアルコール入りの酒を飲んだせいなのか、餓死なのか、結核なのかわからない。それではどのような衛生行政を行えばいいのかわからないということだったんですね」(福永さん)
この申し入れを受けて、「東京都変死者等死因調査規定」が制定され、東京都民政局長(現福祉保健局長)主管の下、東京大学と慶應義塾大学に委嘱して、日本で初めての監察医務業務が始まった。
翌年1947年には、横浜、名古屋、大阪、京都、神戸、福岡を加えた7都市での監察医務業務が行われるようになった。実務は各都市の医科大学に委嘱した。福永さんによると、7都市の異状死を把握できれば、当時の人口の3分の1をカバーできると考えられたそうだ。死を統計的科学的に扱うことができる基盤ができたといえる。1949年には「死体解剖保存法」が公布され、法律も整備された。
だが、1951年の講和条約でGHQの統治を離れる時、監察医務を国の業務としなかったために、地方自治体として負担が大きいとして、京都と福岡が監察業務を辞退した。さらに、1985年の法改正では、事実上廃止状態にあった福岡市と京都市の名前が消えた。
阪神淡路大震災で残されたデータの力
実はこの時、神戸市も廃止の動きがあったそうだ。当時、神戸大学医学部の助手として、監察医務に従事していた福永さんは、教授や大学院生と一緒に、繰り返し厚生労働省に監察医制度を残すようにとファックスを送った。これまでいかに労災認定に遺体の解剖が役立ったかを伝え、今後、国際都市として増加が懸念される輸入感染症に備えるためにも重要な制度だと訴えたという。
「その結果、神戸の監察医制度は残りました。おかげで10年後の阪神・淡路大震災では、2600体の遺体を一週間で監察医がみることができました」
震災では、激しい揺れの後に火災が起きた。焼けた建物の下から焼損遺体が次々に出た。外から見れば焼死に見える。だが専門家たちは、遺体に一酸化炭素中毒の痕跡がないことから、多くの人たちが建物の倒壊で亡くなり、その後、火が回ったことを明らかにした。
この教訓は大きかった。今後も大きな震災に見舞われることが必至の日本で、防火ではなく耐震に力を入れた住宅政策がとられるようになったのだ。これは、未来の命を大きく守ることになるはずだ。
死に向き合うことは未来の安全を作ること
監察医制度がある地域とない地域とは死因の割合にばらつきがある。
「ある地域では、死因に心不全が多い。別の地域では大動脈解離が多いんです」(福永さん)
検案を担当する医師は、確信がもてなくても死亡届に死因を書かなければならない。医師の癖がそのままデータに出てしまう。
東京23区内では循環器系を死因とする例は7割だが、監察医務院が担当しない都下の多摩・島嶼地区では循環器系を死因とする例が8割を超える。
死因が脳出血によるとされる例も多摩・島嶼地区のほうが23区よりも多い。脳出血を外側から診断するために、後頭部の下の部分に針を刺し、髄液を採取してその性状を見る。その技術が不十分で、血が混じるのだ。
外側に異変が現れにくく、病死に間違えられやすい熱中症、凍死、中毒死なども、東京23区内と多摩地区とでは、パーセンテージが大きく異なる。
福永さんはいう。
「地域でしっかり検案されている先生はいる。そうでもない先生もいるかもしれない。問題はいずれにしても死因究明が自治体単位に任されていることです。国ベースでないとデータの解析はできません。異状死全体を見ている私たちは、問題点を発掘することができる。専門家による解析が必要です」
人の死のあり方は社会の急激な変化と連動する。これまでの経験だけでは対応できないことも増えてくるだろう。どの地域にどのような死があるのかを把握し、対策を取ることは、生きやすい社会を作り出すことに直結するはずだ。
死を見つめることは、未来に希望をつないでいく手段ではないだろうか。そんなことを思いながら、東京都監察医務院を後にした。
福永 龍繁
東京都監察医務院 院長。専門領域は法医学。本研究では、自殺・不慮の事故等の要因分析と遺族支援における監察医務院の役割の提言をテーマとする。
杉山 春
雑誌編集者を経て、フリーのルポライター。著書に、『ルポ 虐待 大阪二児置き去り死事件』『家族幻想 ひきこもりから問う』(いずれもちくま新書)、『ネグレクト』(小学館、第11回小学館ノンフィクション大賞受賞)等がある。8月に『自死は、向き合える 遺族を支える、社会で防ぐ』(岩波ブックレット)を出版。
このコラムは平成28-29年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究」によって作成したサイトに掲載されていたものです。研究代表者、著者の同意を得て、このサイトに掲載しております。