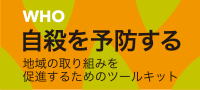幼い子どもたちの「命」と「権利」を守るために不可欠な、死因の分析調査(CDR)
過去10年間に事故等で亡くなった子どもたちは4万人以上にのぼる。そして、そのほぼ9割までが、解剖されず、従って死に至る過程も正確にはわからない。だが、事故や虐待はその背景を理解して対応すれば、防ぐことが可能な場合が少なくない。例えば、幼い子どものうつぶせ寝をやめるよう、政府が通達を出すだけでSDIS(乳幼児突然死症候群)が減った。アメリカやイギリスでは亡くなった子どもたちのレビューは、法的裏付けをもつが、日本にはまだ制度がない。子どもの死と向き合うことで、私たちの社会の課題が見えてくるはずだ。
猪熊弘子(ルポライター)
子どもの死因の不動のトップは「不慮の事故」
本の子どもたちの「死因」のうち圧倒的に多いのが「外因死」だということは、一般的にはあまり知られていない事実かもしれない。人口動態調査が始まった1960年代以来ずっと、14歳以下の子どもの死亡原因の上位に常に入っているのが「不慮の事故」である。2005年の調査では、0歳を除く1~14歳の死亡原因の第1位が「不慮の事故」であった。2015年には0〜4歳の死亡原因の第1位は「先天的奇形等」、5〜14歳の死亡原因の第1位は「悪性新生物」となり、「不慮の事故」は死因のトップではなくなったが、それでも0歳では第5位、1〜9歳では第2位、10〜14歳では第3位で、相変わらず上位にあることは変わりない(ちなみに10〜14歳の死亡原因の第2位は「自殺」である)※1 。
「不慮の事故」が長らく上位に位置し続けている理由のひとつとして、子どもの事故に関する調査や分析が行われて来なかったことが大きい。理由はさまざまだが、まず、東京都以外の地域には監察医が少なく、子どもの死因についてていねいな調査を行うことが出来ない現状がある。解剖することで、亡くなった子どもの体に傷を付けるのはかわいそうだ、という親の思いが優先されることも多い。そして何より最大の理由は、アメリカでは90年代以降、イギリスでも2000年代には法的な裏付けを得て構築された子どもの死亡原因の調査分析「Child Death Review」(CDR)の仕組みが日本にはない、ということである。
「防ぐことができる死」が多すぎる
2016年8月、「子どもの事故」を防ごうというキャンペーンを行っている朝日新聞が、「CDR」の重要性を示唆する調査研究について報道した。子どもの事故に詳しい緑園クリニック院長の山中龍宏氏と、日本子ども虐待防止学会長で国立成育医療研究センターの奥山真紀子氏という2人の小児科医の協力の下、海外のCDRを参考に、過去10年間の日本の子どもたちの死亡事故について調査、分析したものだ(2016年8月28日05時11分朝日新聞デジタル )。この記事によれば、過去10年間で死亡した子どもは4万6086人いるが、解剖記録があるのは4952人分。そのうち1916人に事故や虐待など、予防できる可能性があると考えられるという。
東京監察医務院院長の福永龍繁氏は言う。
「厚生労働省が平成15、16年にうつぶせ寝をやめるよう通達を出したら、SIDSとされる死亡数が極端に減った。つまり、SIDSとされていたものの中にうつぶせ寝の窒息死が隠れていたということです。それなのに、日本では『母親に罪を着せてはいけない』というような風潮から、『これはSIDSですね』とすることがある。海外の公衆衛生学者や小児科医からみれば『日本だけが、特別に解剖もせずに死因をSIDSとしている。特別な判断基準を設けているのか?』ということになるんです」
実際、日本では、亡くなった子どもの解剖に躊躇する親が多い。痛い思いをして苦しんで亡くなったわが子がかわいそうだという思いから、せめて遺体には傷付けたくない、と考えるからだ。しかし、解剖せず、死因を明らかにしないことは、むしろその子のためにも、遺族のためにもならない。その後の子どもたちのためにもつながらない。福永医師は、監察医として親を説得することも少なくないという。
「この子がなぜ死んだか、いずれ絶対に知りたくなる。この子がなぜ死んだかがわかれば、次に生まれてくる子どもや、同じ病気で苦しんでいる子どものために必ず役に立つ。事故で亡くなる子どもの予防のためにもなる。だから解剖したい、必ず役に立つからと。そう言って、親を説得するんです」
亡くなった子どもの死因について詳しく調査・分析をすることが、後に続く多くの子どもの命を守ることにつながる。日本でも早急にCDRを制度化することが必要だ。日本が1994年に批准した「子どもの権利条約の4つの柱」に掲げられている、子どもの「生きる権利」と「守られる権利」を遵守するためにも、CDRは欠かせない。むしろ、「先進国」として当然のことができていない現状を変えなければならない。
保育施設で13年間に190人の子どもが亡くなっている
筆者は特に0〜5歳の就学前の子どもの事故、特に保育所や幼稚園など、就学前の子どもの保育・教育施設での事故について長らく取材・調査を続けている。病院や保育施設で赤ちゃんを亡くした遺族の会「赤ちゃんの急死を考える会(ISA)」の活動にも関わっている。信頼して預けた先でわが子を亡くしたISAのメンバーの訴えは本当に重い。「二度と自分たちのように悲しむ親と、命を落とす幼い子どもが出ないように」という願いから、彼らが地道に活動を続けて来た結果、厚生労働省は2004年以降の保育施設での事故の調査報告を公表するようになった。
報告によれば、2004年から16年までの13年間で、わかっているだけで実に190人もの子どもが保育施設で亡くなっている(幼稚園での事故は含まれていない)。2015年からは、「子ども子育て支援新制度」という新たな保育制度がスタートし、この制度の下で運営されている保育施設(私学助成で運営されている私立幼稚園や、認可外保育施設をのぞく)での事故には、内閣府への報告義務が課せられた。2018年度からは認可外保育施設にも報告義務が課せられる予定である。しかし、私学助成で運営されている私立幼稚園は事故報告義務の対象外であり、具体的にそれらの幼稚園でどういった事故が起き、何人が亡くなっているのかなどは解らない。幼稚園は「学校」だという法律上の区分がその理由なのだが、本来、どんな施設かは関係なく、「0〜5歳の子どもの施設での事故」という枠で調査するべきだと筆者は考えている。
保育施設で最も多い重大事故(死亡、あるいは意識不明)は、0〜1歳児の睡眠中の事故である。次いで、1〜2歳児の食事中の窒息、3歳以上の水遊びやプールでの事故が多い。これらが繰り返し起きていることから、内閣府は2016年3月に「教育・保育施設等における事故防止及び 事故発生時の対応のためのガイドライン」を作成し、保育施設への注意喚起を行っている。また、2018年度から改訂される「保育所保育指針」「幼保連携型認定こども園教育保育要領」でも、「睡眠中、水遊び・プール、食事中」に事故が多いことが明記され、保育者に対策を求めている。
命を守ることは、ひとり一人の子どもを大切にすること
保育施設での子どもの事故には、「こうすれば確実に防げる」というものがない。「保育」はゆらぎのある「人間同士の営み」だからだ。子どもたちひとり一人の個性や、保育者の経験や知見、保育施設の建物や園庭の設備の状況、子どもたちの遊びの中身、気候など、日々、様々な条件が異なってくる。昨日は事故がなくても、今日は起こるかもしれない。
拙著『死を招いた保育』(ひとなる書房)は、2005年8月10日、埼玉県上尾市にある上尾保育所で起きた、4歳の男の子が保育所内の本棚の下の引き戸の中に入り込んで熱中症で亡くなるという事故について書いたものである。
筆者の取材によれば、そこでは「自由保育」という名の下に子どもたちが放置、放任され、保育者たちは子どもの悪いところばかりをネガティブに見て叱り倒す、極めて冷たい保育が行われていた。保育者や保護者同士の仲が悪く、大人達の関係は最悪で、そのために8人の保育者が気づいていた「本棚」の危険を共有することができなかった。上尾保育所事件以降、筆者は何度も保育事故の取材をしてきたが、同じように「組織」の問題が事故につながった事例が少なくない。特にパワハラがあるなど、上から下への命令が絶対的な組織では、保育者たちは普段から「言われたことだけやっていればいい」として考える力を奪われている。安全について自分から考え、動くこともなくなり、いざ、事故があった時には誰も動けず、さらに事故が大きくなる傾向がある。そして、そういう施設ほど「自分たちは悪くない」と主張し、事故の責任を子ども自身に押しつける。明らかに組織的なミスによる死亡事故としか考えられないのに、亡くなったのは子ども自身の病気のせいではないかと主張することさえある。CDRがないことで、組織の責任が隠蔽される危険もあると筆者は考えている。
保育そのものの中身、そして「組織」のあり方が事故と大きく関わっている。死亡事故を防ぐためには、人間同士のネットワークを強固なものにし、保育者や保護者同士が互いに信頼しあい、ていねいな関わり合いをしていくことが、実は最も大切なことなのである。
保育施設で守るべき子どもの「いのち」とは、ただ子どもが生きていれば良い、ということではない。「いのち」とは、子どもひとり一人の存在である。子どもの発達を守るため、いくつかの危険とも向かい合わなければならないが、その中で、子どもひとり一人の存在、つまり「いのち」と確実に向き合う姿勢を持つことが、遠回りでも子どもの事故を防ぐことにつながっていくのである。
※1:子どもの事故防止関連「人口動態調査」調査票分析〜事故の発生傾向について(平成28年11月2日 「第2回子供の事故防止 関係府省庁連絡会議」 資料 消費者庁消費者安全課)より。
執筆者:猪熊弘子
ジャーナリスト・東京都市大学人間科学部客員教授・(一社)子ども安全計画研究所 代表理事。 お茶の水女子大学大学院 博士課程後期(保育児童学領域)在学中。日本の保育制度や歴史、待機児童、保育事故について20年以上にわたり、取材・執筆・翻訳を行ってきた。現在はイギリスなど海外の保育・教育制度についても研究し、保育の質、評価論にも詳しい。双子を含む4人の子の母。著書多数。『死を招いた保育』(ひとなる書房)で第49回日本保育学会 日私幼賞・保育学文献賞受賞。
このコラムは平成28-29年度厚生労働科学研究費補助金障害者政策総合研究事業「外因死の背景要因とその遺族への心のケアに関する研究」によって作成したサイトに掲載されていたものです。研究代表者、著者の同意を得て、このサイトに掲載しております。